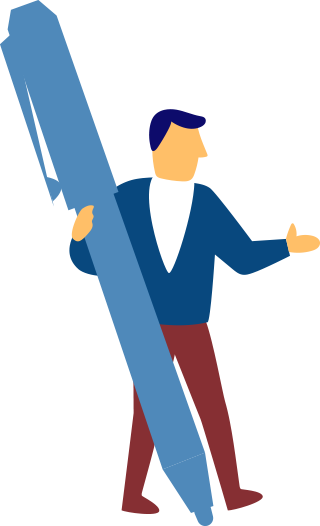既存・新規問わず、ビジネスを展開していくためには「新しいアイデアの創出」が欠かせません。
しかしながら、限られたメンバーで案出をしていると、どうしてもアイデアが枯渇してきてしまうもの。
そこで今回、株式会社東海理化が取り組んだのが、
「異なる部署が楽しみながらアイデアを創出できる共創アイデアソン研修」です。
「アイデア出しフレームワークの新たな学び」「部署間の壁」といった課題感がどのように変化したのでしょうか? 本イベントの事務局メンバーと参加者、双方に話を聞きました。
■お話を伺った方々(※部署は研修当時のものです。)

<事務局>
株式会社東海理化 ダイバーシティ推進室 中田 奈緒 様(左) 加藤 由香 様(右)

<参加者>
株式会社東海理化 性能実験部 原澤 誠 様 株式会社東海理化 シフター技術部 加藤 礼杜 様
変わりゆく自動車業界の流れにどう立ち向かう?
最大の課題「部署間の壁」払拭への第一歩
愛知県に本社を置く株式会社東海理化は、自動車用スイッチやシフター、シートベルトなどさまざまな自動車部品を企画・開発から量産まで一貫して自社で行っている企業です。既存の製品を生み出すことはもちろん、新製品を開発することも大きなミッション。そのため、効率良くアイデアを出し合ったり、部署間でも情報を共有して開発を進めたりしていくことが重要です。
「自動車業界を取り巻く環境が刻々と変化し、これまでのように各々が自分の部署だけでミッションを遂行していくには限界があるなと感じていました。しかし、異なる部署とコミュニケーションを取りながらアイデアを出し合うことで新しい発想が生まれると思いつつ、現状の東海理化は部署間に壁があると感じていたのも事実。他社との異業種交流にも力を入れているのですが、一方で社内に目を向けてみると、限られたメンバーとしか交流していない事実に気がつきました」(事務局・中田さん)
そんな課題解決に向けた第一歩として、社内向けのアイデアソンワークショップを開催する運びとなりました。
「以前からアイデアソンやハッカソンを社内で実施してみてはという声があり、インターネットで検索したり、新規事業に携わる部署から情報をもらったりして複数社を比較検討した結果、HackCampさんに依頼することに決めました。主にバックキャスティングでのイベント内容をご提案いただいたのですが、その思考の展開法自体がとても勉強になりました。さらに、描いたありたい姿に近づくためには、ただ参加して楽しいイベントで終わらせるのではなく、持ち帰り感があるものにしていただけたことが大きかったです」(事務局・加藤さん)
「今回のイベントで出会った他部署との関係性が参加後も続くように、体感した共創メソッドをイベント後も使えるように、といった形でいろいろなアイデアをいただきました。本当に、限られた予算内で私どもがやりたい内容を的確に、しかも解像度を上げて表現し、頭の中でモヤモヤしていたものを形にしてくださったことが、HackCampさんにお願いした決め手でしたね。弊社のビジョンからしっかりと理解し、親身になって寄り添い伴走していただきました」(事務局・中田さん)
体を動かし、初対面の相手とも会話をしながらアイデアを生み出す!
「リアル対面型共創アイデアソン研修」
複数回にわたるヒアリングとミーティングの結果、実施したのは2部制のワークショップ。
1部では「部署間の共創を促進する環境づくりをするアイデアとは?」をテーマに、4つの手法に取り組みました。
1部
・アイデア創出:マンダラート
・アイデアブラッシュアップ:スピードストーミング
・アイデアをまとめる:アイデアスケッチ
・アイデアを選ぶ:ハイライト法
続く2部では「業務でも使えるアイデアメソッド」を生み出すために、
AIを用いた「共創ナビivan(イワン)」(以下、ivan)を活用しながらアイデアのブラッシュアップに努めました。
2部
・課題設定:問いづくり(QFT)
・ありたい姿を描く:マンダラート
・解決策策定:生成AIプロンプト
・アイデアブラッシュアップ:PPCO
「これまでにもワークショップを企画したことはありましたが、今回のような全社向けのアイデアソンは初の試みでした。手挙げ制だったので、最初から参加者の意欲が高かったことはもちろんですが、特に前半は体を動かしながら、はじめましての方とも話をしながらアイデアを出し合い、議論が盛り上がっていて、事務局としてもうれしかったですね。部署間の壁がなくなったとまでは言えないにしても、活発な交流ができたと感じています」(事務局・中田さん)
「今回、職場に戻ってからも活用できるお土産をいただきましたが、それがすごく参加者に喜ばれていたのが印象的でした。アイデア創出のヒントになるようなワードが書かれていて、ちょっとアイデアに行き詰まったときに見るとすごく役立ちます。お守りみたいな存在として持ち歩いているという声もありましたね」(事務局・加藤さん)
企画・運営をした事務局メンバーの言葉から、確かな手ごたえを感じた様子が伝わってきます。一方、実際に参加した方々は、今回のワークショップに対してどのような感想を抱いたのでしょうか。率直な意見を聞いてみました。
「社内の別の部署の人、ほぼ初対面に近い人と会話ができ、リアルイベントの良さを再認識できました。ちょっとした雑談のなかから得た気づきも多かったです。AIの活用に関しても、とてもよく練られた方法だなと感動しました。あの日あの場所だけで理解しきるのは相当しんどかったですが(苦笑)。欲を言えば、参加者同士の交流の時間がもっとあるとなお良かったです。1週間おきの全2回にして、間で参加者の交流を深めたり、宿題を進めたりといった内容もいいかもしれません」(参加者・原澤さん)
「私は普段、決まった部署の決まった相手と仕事を進めることがほとんどなので、いろいろな意味で刺激を受けました。少なくとも20名以上はアイデア出しに興味がある人が社内にいるということがわかりましたし、考えていた範疇より進んだアクションを起こしている人もいたことにも驚きました。もっと自分もチャレンジしていいんだ!と思えましたね。今回の参加の動機が『アイデアの発想の手法を学びたい』という想いだったのですが、初めて知ったいくつもの手法を実際に試せたことが大きな収穫でした。期待以上の成果が得られたと感じています」(参加者・加藤さん)
イベント後に行ったアンケートでも、参加者の約9割近くが「このワークショップを人に勧めたい」と回答しており、満足度の高さがうかがえる結果となりました。
活用のカギはワークショップ後の行動にある。
自部署に戻ってからの参加者の動きに注目
大好評だった本アイデアソンですが、本当の真価が問われるのはワークショップ終了後。
今回の学びをもとに、参加者の行動にどのような変化が起こったのかを尋ねました。
「私が所属しているのは、どちらかというと企画寄りではなく、ルーチンワークが多い部署なのですが、そのなかでもPPCOを自分で壁打ちとしてやってみたり、『ivan』を周りに紹介してみたりしています。生成AIをちゃんと手順に従って活用していくと、かなり可能性が広がりますね。うちの会社は職種が幅広いため、もしかすると一部の部署の人しか活用が難しいかもしれないと思っていたんです。でも実際に体験してみたら、どんな部署にもアジャストされていた内容で、今後変化していく東海理化の中でさらに活用できるなという感触が持てました」(参加者・原澤さん)
「早速、新製品のアイデア出しのときに『ivan』を使ってトライしてみました。また、上司や同僚にも紹介しています。やはりワークショップの時間だけでは足りなくて、実際に自分で使ってみたことで気づいた点がたくさんありますね。また、近々会社に新棟が建つのですが、そのなかに共創スペースを作ろうという話が出ています。どんなスペースにして、どう活用していくかを相談するワークショップにも参加しており、そちらでも活かせる経験と知識を得ることができました」(参加者・加藤さん)
最後に、今後ワークショップを開催するとしたら、どんなことにチャレンジしたいかを事務局、参加者それぞれに尋ねました。
「今回、アイデアをみんなでディスカッションしましたが、どうしても時間が来たらそこで終了になってしまいます。もう少し踏み込んでいきたいですよね。期限を設けてなにか仕上げなきゃいけないとか、プレッシャーを感じつつ、少しの苦しみも味わいながらディスカッションを深めていけるような内容がいいのではと思います。やはり会社でやっている以上、学べて良かった面白かったで終わらせず、何かを生み出していきたいです」(参加者・原澤さん)
「リアルに新商品を作り出すミッションがあってもいいと思います。各チームで競いながらアイデアを出し合って、最終的には製品を作っちゃうとか。技術系の部署の人たちだけじゃなくて、事務系の人とか、いろんな部署の人のアイデアをミックスすることで面白い化学反応が起こることが期待できます。東海理化のためにもなるので、そんな機会があればぜひ参加したいです」(参加者・加藤さん)
「原澤さんがおっしゃったように、異業種交流会を行っても交流をしてそこで終わりになってしまいがちなので、その点は工夫していきたいですね。とは言え、私たちの部署だけでは実現が難しいかもしれないので、各部署と連携して出たアイデアを深掘りしたり、アウトプットとして成果物が出せるような企画を考えたいと思います」(事務局・中田さん)
「今回のワークショップの募集をしたとき、『参加したいけれど職場で手を挙げづらい』『業務が忙しくて参加できない』といった声がありました。そんな人たちがどうしたら参加しやすくなるか、アイデアを学ぶ横のつながりを作ったり、積極的に参加できるような風土を醸成したりといった点にも注力していきたいです」(事務局・加藤さん)
HackCampが提供したワークショップを機に、東海理化は大きな一歩を踏み出しました。
この先、どのような新しいアイデアを生み出し、自動車業界を変革していってくれるのか、期待しています!
目的
課題
効果
導入の決め手
時期
2024年10月
参加人数
25名